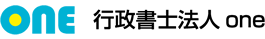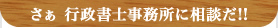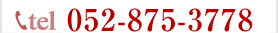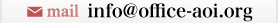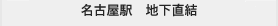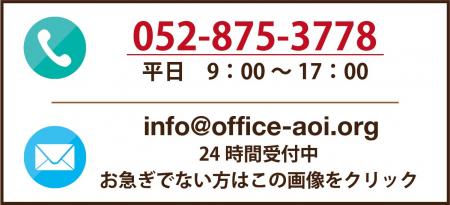『三好のブログ|名古屋の行政書士』カテゴリーの投稿一覧
技能実習(育成就労)・特定技能で訪問介護解禁!?条件は?
2025年3月5日(水)
技能実習,特定技能,育成就労,介護,訪問系,訪問介護,外国人,サービス
訪問介護解禁までの経緯
訪問系サービス解禁の始まり
技能実習制度や特定技能制度において介護の外国人受入が始まった際に、施設系の介護事業者しか受入対象とされなかったことから、訪問系の介護事業者の受け入れを認めてほしいという要望は非常に強いものがありました。
訪問系サービスは、利用者と当該外国人が1対1でサービスを行うことが基本であることから、指導体制や権利保護等様々な観点から対象外となっておりました。
しかし、2024年6月26日の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめ(中間報告)において、
「外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期就労することが重要であることから、介護福祉士の資格取得含め後押しが必要である」ということから、
「日本人同様に介護初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの質や権利保護等の観点から、事業者に一定の遵守事項を履行できる体制や計画を求めることを条件として、外国人介護人材の訪問系サービスの従事を認めるべきである」という趣旨の報告がなされています。
訪問系サービス解禁の経過
皆さん、御存知の通り、育成就労・特定技能制度(いわゆる新制度)の基本方針を定めるための有識者会議が現在執り行われております。
「第1回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が、2025年2月6日に開催されました。
この分野別運用方針について、介護分野の方針改正の案の提出がありました。
改正案において今までは、訪問系サービスは対象外とするという文言を削除し、訪問系サービスに従事する場合に一定要件を満たさないといけないという内容が盛り込まれました。
これにより、訪問介護(訪問系サービス)解禁 確実か!?となり、熱が一気に再燃しました。
訪問系サービス従事の要件は?
第1回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 のときの案
外国人本人に対する要件
①介護職員初任者研修課程「等」を修了
所属機関(受入企業)に対する要件
①1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
②一定期間、責任者等が1号特定技能外国人の訪問介護に同行するなど訓練を行うこと
③1号特定技能外国人に対して、訪問介護等における業務内容の説明、意向の確認、キャリアアップ計画の作成
④ハラスメント防止の相談窓口を設置
⑤1号特定技能外国人の訪問介護等の業務の際の不測の事態に対応できるよう情報通信技術を活用して環境を整備すること
第2回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 のときの案
第一回の有識者会議後に上がった意見を踏まえ要件が少々変わりました(個人的にはかなりハードルが上がりました。)。
外国人本人に対する要件
①介護職員初任者研修課程「等」を修了
②実務経験等を有する
※1年以上の実務経験を想定
所属機関(受入企業)に対する要件
①1号特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
②一定期間、責任者等が1号特定技能外国人の訪問介護に同行するなど訓練を行うこと
③1号特定技能外国人に対して、訪問介護等における業務内容の説明、意向の確認、キャリアアップ計画の作成
④ハラスメント防止の相談窓口を設置
⑤1号特定技能外国人の訪問介護等の業務の際の不測の事態に対応できるよう情報通信技術を活用して環境を整備すること
※これらを実質的に有効なものとするために以下のような具体的内容を想定。
・ハラスメント防止のために、対応マニュアルの作成、管理者等の役割の明確化
・ハラスメント発生の際のルールの整備、実施
・利用者や家族等への周知
・外国人介護人材の相談窓口の整備
→これらの体制を整備し、履行できる体制・計画の構築を条件とする。
※更には上記について、巡回訪問時の監査事項となることを想定
訪問系サービス解禁の今後
今述べた要件は、2025年3月4日時点のものであり、これから更に議論を重ね、変わっていくことが想定されますので確定事項ではありません。
しかし、2025年3月の閣議決定・4月からの運用開始を目指していますので、大きくブレるようなことはないように思います。
しかしポイントはまだまだ残っていますので注目しておく必要があります。
訪問系サービスはどの業態まで認められるのか?
現時点(2025年3月4日)では、
サ高住(サービス付き高齢者住宅)のような、不動産賃貸業に介護サービスを付加したような業態まで認められるのか?
居宅系のものはすべて認められるのか?
など、は不透明な状態です。
しかし、製造業のような標準産業分類による縛り等も予定されていないようなので、介護指定書があるのであれば、サ高住のような業態、居宅系のような業態かかわらず認められるのではないかと予想します。
訪問看護などは、介護とは異なるため認められないかもしれないですね。
運用開始後の温度感の予想
当初から予定されている「初任者研修等」をいつ受講するのか?
という点と、
第2回で追記された要件である、「1年以上の実務経験」が、
ハードルになってくる可能性が高いです。
初任者研修に関しては国内での受講となるので、海外から呼び寄せる(入国させる)パターンの受入の場合は、入国後に受けることが原則になりそうです。
特定技能として在留資格を取得する前に、来日して受講するのであれば、それはなんの在留資格でやるのか?どのような段取りで実施するのか?あたりがポイントになりそうです。
1年以上の実務経験については、海外での経験が認められるのかどうかは定かではありません。来日後特定技能としての経験が求められるのであれば、そもそも訪問系のサービスしか行っていない事業者は、国内で実務経験を持った人の転職を待つしか道がなくなってしまいます。
この辺は、今後議論で整備されていくのだと思いますが、現状このような感じです。
技能実習制度の訪問系サービスは?
今までは、新制度の有識者会議の話でしたので現時点では主に特定技能に関する話でした。
ではもう数年は継続される技能実習制度で訪問系サービスの解禁はあるのでしょうか?
技能実習評価試験の整備に関する専門家会議 第86回
技能実習制度における技能検定(評価試験)に関する会議において以下の議論がなされています。
・介護職種の作業範囲拡大(訪問系のサービスの追加)が了承された
よって、技能実習制度にも訪問系サービスが解禁されることは間違いないと思いますが、特定技能と同時(2025年4月スタート予定)かどうかは微妙なように思います。
了承と同時に以下のような言及もあったためです。
・技能実習生へ周知期間を十分にとって現場が混乱しないようにすべき
おわり
いかがでしたでしょうか?またアップデートがありましたらお届けいたしますのでぜひ御覧いただけばと思います。
また、訪問系サービスに置いて求められる体制の整備や計画の作成など、弊社でも承れますのでお気軽にご相談ください。
社会福祉連携推進法人とは
2021年11月15日(月)
社会福祉連携推進法人,監理団体,設立,技能実習生,介護,認定,名古屋,行政書士
はじめ
社会福祉連携推進法人という法人形態、みなさんご存知でしょうか?
知る人ぞ知る感がありますね。
我々監理団体等の外国人ビザの手続きを専門とする行政書士にも実は最近話題になりました。(個人的に!?)
このページをご覧の皆様方におかれましては、社会福祉連携推進法人を設立したい、あるいは、すでに設立してあり監理団体になりたい、または、なんだか興味があるという方々と思います。
以下にて、社会福祉連携推進法人丸わかり解説をしてみたいと思います。(半わかりくらいかもしれません)
社会福祉連携推進法人を知るためには社会の構造変化を捉えることが重要
もちろん皆さんご察しの通り、新しい法人形態です。私も聞いたことがなかったくらいでしたw
新しくこのような法人形態ができたということは、社会にその必要性があるということを意味します。よってこの法人の趣旨を理解するためには見出しの通り
社会構造について少し復習しましょう。(物騒な事件が多いですが、社会に復讐はしてはいけません)
高齢者急増からの減少と若者が・・・・・
さて、皆さんに問題です。日本の人口ピラミッドは、今後10年、20年でどのように変化していくでしょうか?
え?もうすでにピラミッドじゃない?
その通りです。
なんか土偶みたいだよねw土偶ってw(土偶を知らない人は調べてね)
余計なことばかり言って行を稼いでないか?
いや余計なこと言うからボリューム増えすぎんだよw
じゃあね一言で言うよ。
ダイバーシティ だよ ダイバーがたくさんいる街じゃないよ。
ほらわからんでしょ!
ちゃんと聞きなはれ。(一人芝居に疲れてきた・・・)
(現時点A4一枚約700文字そろそろブログとしてはシメに入っていい頃合い・・・ってなんも伝えてねえw)
日本の人口動向について皆さんご存知のことを述べていきますね。
2025年に向けて高齢者は爆増すると言われてます。ってか爆増してる。
そしてそこをピークに高齢者は爆増からちょい増になっていきます。
ちょい増ってかわいいね
ちょいまし じゃなくて ちょいぞう ね。
なんなら地方では、高齢者も減少傾向が始まると言われています。
もちのろん 若者(生産年齢人口)の減少も爆っていきます。
爆減!?!?
するとどうなるか。
年金が払えねえ・・・
ではなく、共同体(まあ小さな社会みたいなもの)がどんどん失われていきます。
心も失われて・・・(もう余計なこと言いません)
そうすると、集団から個へとニーズの中心が移動していくことになります。
そうして今流行語大賞の「ダイバーシティ」となるわけです。
ダイバーシティとは、まあ多様性とよく言われるように、いろいろなサービスに対するニーズが複雑化・多様化していくこと、らしいっす。
わかるわかる・・・
で、今回は、子育てや介護、生活困窮などの福祉分野にスポットを当ててみたけど
やっぱ多様化やんけw
ということで、非営利セクター(主に社会福祉法人を想定)が中心となって専門性やニーズへの対応をおこなってかなければならん と
一法人には難しいから 手を組んで やっていきましょー
って感じ。
(だんだん雑になってきた。。。)
で、それを社会福祉連携推進法人でやろうとしているわけなんですね。
名前長い。画数多い。まあ書かないけど。
2.社会福祉連携法人の組織構成(運営)ってどうなの?
なんかすげえことやろうとしてるのはわかった。じゃあどうやってやんのよ?
ってなりますよね。
うんうん。
ここは皆さんがわかりやすい株式会社と比較しましょうか。
いや実は株式会社では比較難しいんすわ・・・社福と組合足して2で割った感じだよ☆(伝われ)
・・・まあとりあえず登場人物から紹介しましょうか。
- 社会福祉連携推進評議会
- 社員総会
- 理事会
が主な企業ガバナンスですね。お、初めて法律家っぽい言葉使った。
(1)社会福祉連携推進評議会について
社会福祉法人の評議委員に名前が似ていますが、だいぶ異なります。
なんで紛らわしい名前つけてわかりにくくするんだろう頭のいい人たちは。
社会福祉法人の評議委員は、株式会社でいう株主に似ており、法人の重要事項を決定します。
一方、社会福祉連携推進評議会には、議決権はなく、意見を述べるにとどまっています。
株式会社と契約した顧問弁護士や顧問税理士のようなイメージの方がしっくり来るかもしれません。
どんな人がなれるかと言うと
・区域内の福祉の状況の声を反映できる者
を必ず入れることとなっています。
その他、業務に応じて
・学識有識者
とか
・経営者団体
とか
・福祉サービス利用団体
などが想定されています。
区域内での社会福祉ニーズの吸収及び社会福祉連携推進法人への反映、中立的意見具申が求められます。
任期は4年。3名以上から定款で定めます。
ちょっと待て。「区域」って何!?と思った方は優秀です。
組合の「地区」と似ていますが違います。
組合の地区は、「組合員の加入条件」として新たな加入者の事業所の所在地を問うものです。
一方、社会福祉連携推進法人の区域は、「社会福祉連携推進法人が業務を実施する地域」を指します。ただその範囲を決めるのに特段制約はなさそうですが・・・。
(2)社員総会について
こちらは、組合でいう組合員総会、株式会社でいう株主総会ですね。
社員というのは従業員ではなく、オーナーを意味します。つまり、株主と同じような立ち位置です。合同会社なんかも出資者は社員ですよね。
原則は、1社員に1票です。ここは出資数に応じて議決権が増える株主とは違いますね。一方、組合の組合員とは同じです。
社員になれるのは
・社会福祉法人
はじめ、社会福祉事業を経営する法人などです。
人的な集まりのため、2以上の社員がそもそも必要です。
(3)理事会について
これはわかりやすい。株式会社でいう取締役会。組合でいう理事会(同じですね)です。
業務の執行に関する意思決定機関です。
もちろん理事で構成されます。
理事になれるのは社会福祉法人と同じような条件で、社会福祉に識見を有する者等とされています。
ちなみに理事の任期は2年、6名以上必要です。
(4)監事について
社会福祉連携推進法人における役員は、理事だけではありません。
監事も必置機関となっています。
監事の業務は、理事のお目付け役です。悪いことすんなよwと。
財産管理について識見を有する者から選任し、任期は2年。2名以上必要です。(役員等と親族関係などある場合には制限されます。なぜならお目付け役だから母ちゃんではだめっすw)
(5)会計監査人について
こちらは、一定規模以上となるに必置機関となります。
一定規模とは、収益30億円又は負債が60億円を超える場合です。
公認会計士や監査法人等から選任し1名以上置きます。任期は1年で何もなければ(社員総会で文句でなければ)自動で再任となります。
もちろん第三者的関係性のある会計士等でなければいけません。
3.社会福祉連携推進法人の業務
で、結局何やるんだよって話ですよね。以下に説明します。
想定されているのはこの6つの業務です。
①地域福祉支援業務
②災害時支援業務
③経営支援業務
④貸付業務
⑤人材確保業務
⑥物資等供給業務
なんかぱっと見、組合っぽい・・・・・
(1)地域福祉支援業務について
・地域貢献事業の企画立案
・地域ニーズの調査
・事業のためのノウハウ提供
等が想定されているようです。
組合でいう「教育情報提供事業」みたいですね。
(2)災害時支援業務について
・応急物資の備蓄提供
・被災施設利用者の移送
・避難訓練
・BCP策定支援
等が想定されています。
緊急時に皆で力を合わせて乗り切ろう(起きた時の備えもしておこう)といった感じですね。
組合の共同事業でこれやるのもアリかも・・・
(3)経営支援業務について
・経営コンサル
・財務状況の分析・助言
・事務処理代行
などを行います。
組合でいう「共同専門家サービス」みたいですね。
全部組合www組合愛すさまじいですね。私。
ちなみに、社会福祉連携推進法人の技能実習生受け入れ事業(監理団体業務)はここの枠になるようです。
※(5)の人材確保業務ではありません。なぜなら技能実習生は人材確保でなく技能移転だから・・・・・・・だと思う。(まだそれにこだわるかw)
(4)貸付業務について
・社員への資金の貸付
これも組合にある事業ですねw
貸付の度に認定が必要となったり、いろいろと制約厳しめです。
(5)人材確保業務について
・採用・募集の共同実施
・研修の共同実施
・現場実習の調整
など人材の資質向上や採用コストの削減が目的です。
組合でいう「共同労務管理」・・・・もう組合で良くない!?!?
(6)物資等供給業務について
・紙おむつやマスク等の一括調達
・給食の供給
など。
組合でいう共同購買とか共同販売とかですね・・・・
結論を発表します。
本当に、新しい法人か!?既存のパクリでは・・・発想力に乏・・・・・・(以下略
4.最後に作り方。
(1)設立のフロー
でね。社会福祉連携推進法人がどーのこーのいってきたけどね。
オチを伝えますと、
まず作るのは実は、一般社団法人wwwww
そこから公益社団法人になるイメージで、社会福祉連携推進認定という行政のお墨付きをもらって鞍替えすんのよ。えー。なんそれ。
(かしこい人は今のうちに一般社団法人作るといいよ。社会福祉連携推進法人の認定は令和4年度からでっす。現時点、詳細まだまだ未定。)
| 一般社団法人設立 |
① |
設立内容の決定 | 定款の内容、役員、会費、業務内容等を決める。 |
| ② | 定款認証 | 定款を完成させ公証役場にて認証。 | |
| ③ | 設立時役員による調査 | 設立手続きが法令及び定款とおりなされているかを確認。 | |
| ④ | 設立登記 | 法務局にて一般社団法人の設立登記。 | |
| ⑤ | 社員総会 | 社会福祉連携推進法人の方針や財務諸表の承認などを決定することにより社会福祉連携推進法人への変更を決議 | |
| 社会福祉連携推進法人へ変更 | ⑥ | 社会福祉連携推進認定の申請 |
所管行政に申請。 ※必要書類、申請先は後述。 |
| ⑦ |
社会福祉連携推進認定がおりる |
同時に公示されます。 | |
| ⑧ | 名称変更登記 | 法務局に、一般社団法人から社会福祉連携推進法人へ変更する旨を登記。 |
(2)認定手続き(まだ案です)
この辺からはまだまだ(案)状態ですが、現時点のものをお知らせしますね。
ⅰ.申請先について
【原則】
☆「都道府県」に申請
以下の場合は、それぞれ例外が適用
【例外①】
☆特定の一つの市のみを区域とする場合→その「市」に申請
例1)区域は名古屋市のみ→名古屋市に申請
例2)区域は安城市のみ→安城市に申請
【例外②】
☆市が複数だがすべて一つの県内であり、かつ、主たる事業所が政令指定都市→その「政令指定都市」に申請
例1)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が名古屋→名古屋市に申請
例2)名古屋市・春日井市・豊明市を区域とし、主たる事業所が豊明市→愛知県に申請(原則を適用)
【例外③】
☆2以上の地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)にわたって区域とする場合、かつ、①or②のどちらかの場合→「国」に申請
①「社員」の主たる事業所がすべての地方厚生局にわたり、かつ、すべての業務を行う場合
②「社員」の主たる事務所がすべての都道府県に所在し、かつ、2つ以上の業務を行う場合
このケースはなかなかないですね・・・
これら以外はすべて「都道府県」への申請となります!
ⅱ.要件について
①主たる目的
定款の目的の記載事項に必要な記載があることと、社会福祉連携推進業務の事業費の割合が過半数を超えていることが重要となります。
②社員の構成
社員は法人のみ。2以上。過半数が社会福祉法人であること。など
③知識・能力・財産基礎
必要な機関がすべて備わっていること。業務の実施体制、収入の見通しなど。
④社員の条件に不当なものがないこと
社員になる又はやめるというときに不当な条件があってはならないこと。
⑤定款への記載内容
13個ほどあります。
ⅲ.必要書類について
①申請書
②定款
③社会福祉連携推進方針
④登記事項証明書(一般社団法人の)
⑤役員名簿
⑥基準を満たしていることを証する書類
これは、詳細がまた別途出ると思います。
⑦欠格事由に該当しないことを証する書類
これは誓約書の様式が作成されると思います。
⑧社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書、就任承諾書
⑨社員名簿
⑩役員の履歴書・就任承諾書
⑪財産目録
⑫事業計画、収支予算書2年度分
⑬その他必要と認められるもの
結構大変かもしれませんね。
そもそも組織構成が複雑なので書類がどうこうというより組織自体がわかりにくいので
初めて申請するのにはなかなか骨が折れるかもしれませんね。
5.当社のサポート
当社では、一般社団法人の設立から社会福祉連携推進認定、さらには監理団体許可申請まで一括でご相談または、書類の作成・行政とのやりとり、そのコーディネート、設立後の運営サポートなどを
お受けすることが可能です。
ぜひご相談ください。
コロナ禍:在留資格「特定技能」申請依頼急増!特に増えた分野と注意点はこれだ!|圧倒的実績名古屋行政書士
2021年5月18日(火)
名古屋行政書士|在留資格ビザVISA|特定技能技能実習|介護建設外食|フィリピンベトナム|推薦者表POLO|行政書士法人one|実績多数
在留資格「特定技能」の現状・現況(当社比)
皆さんこんにちは。
行政書士の三好です。
最近、帰国困難の技能実習生や就職難+帰国困難の留学生が増えた関係から
特定技能への移行がグッと増えた印象です。
(※当社調べ)
特に、介護・建設などコロナの影響を大きく受けていないものの人手不足が前々より顕在化していた業界に増えた印象です。
介護は、在留資格「介護」という更新に制限がない就労資格へのロードマップが明確になりつつあることから留学生に増えました。
建設は、技能実習や建設特定就労からの移行ですね。
(※当社への依頼ベース。全国統計ではありません。)
宿泊や外食分野は特定技能の法改正後、コロナ禍までは非常に注目が高まっていましたが
今は・・・
日本がどれだけインバウンドに頼っていたかよくわかるとともに
世界に誇れる観光国家であることがわかりました。
特に私は沖縄や東京への訪問・滞在が多いので本当に痛感します。
そんな中、外食分野は少し申請依頼が盛り返してきた気がしています。
(※当社データより。しつこい?笑)
国籍は、当社がPOLO申請について一定の経験があることから
フィリピンが多いですが、あとはベトナム・インドネシア・中国・スリランカ・ネパールと、全国統計とさほど遠くないと思われます。
そこで、留学生からの特定技能移行、技能実習からの特定技能移行で
当社が実際に「マジかよw」ってなった注意すべき点や
「予想はしてたけど・・・」ってやつを
記載しておきますのでみなさんご参考にどうぞ!
(参考になるかは保証しません。)
特定技能移行の注意点
留学から特定技能への在留資格変更許可申請
留学生からの特定技能移行で圧倒的に多い問題が
・週28時間の資格外活動許可(アルバイト)を超えて働いているいわゆるオーバーワーク
と
・当然多く働いているので結構な額の住民税・国民健康保険・国民年金がかかっています。学生の特例などを申請して「合法的に」払わなくてもよい状態になっている子も多いですが、支払い請求をシカトかましている子の方が圧倒的に多いです
(※盛りました)
さて。このような場合にどうしたらよいか。
まずはオーバーワークについて
どこでどれくらい働いているか正直に報告します。
割と平気でバイト先数カ所誤魔化して報告してくる留学生は多いです。
課税証明などと照らし合わせるとすぐにバレます。
正直にどれくらい多く働いたかを聞き取りまとめた上で
・なぜそのような事態に陥ったのか(留学生としてスポンサーがいるはずなのに何故)
・反省の有無
・今後の法令遵守の誓約及び誓約の信頼性
などの説明や反省文により、見逃してもらうというと語弊がありますが
在留状況が不良という状態を少しでも和らげます。
もちろん未納状態のものは全て支払うもしくは、分割納付の計画書や契約書により支払いの実現可能性を示します。(もちろん更新時は履行している必要があります。)
登録支援機関等の委託を受けている場合は
役所に同行して手続きしていかないといけないためとても手間と時間がかかります。
何度も経験してますが
マジで大変っすw
さて技能実習生からの移行の場合どうでしょう。
技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請
技能実習生からの移行でよく問題だなと思うのは
(コロナ特例の雇用維持支援「特定活動」絡みはとりあえず無視します)
・監理団体がよくわかっていない
・企業もよくわかっていない
・送り出し機関が暴走
です笑
本当にやばいなと思うのはあまりにもひどい監理団体が多い。
僕は結構(日本でもトップクラスと思う※当社調べ)技能実習に関して顧問先や申請案件多いので
できる限り監理団体の方を持ちたいところなんですが。
「この組合やばw」と本気で思うことが週一くらいであります。
もちろん、うちの顧問先はそんな組合ありませんし、優良な(技能実習法的な優良ではなく、倫理的な優良)監理団体の方が多いことは分かっていますが。
うちに来る案件だけでこんだけ頻繁にやばいと思うのだから注意喚起せずにはいられません・・・。
じゃあ、どんなところでそう思うの?って話なんですが
本当にやばすぎ(一言で言うと、無知は怖いもの知らずすぎ)て細かく書きませんが
まあそんなこんなのトラブルで
・実習がきちんと終了してなかった
(在留状況不良)
とか
・入国時と実習生の履歴書違うがな
(虚偽申請)
とか
・検定なんて受けさせなくていいっしょ
(実習計画との齟齬、誓約違反、目標未達成)
とか
とk・・・もうやめときます。
監理団体がやばいと(履歴書は送り出し機関ですが・・)
なんでそうなるのか!?みたいな案件が多発します。 気をつけてください。
中退・除籍の留学生と技能実習中断の実習生は特定技能とれない!?
さて、上記の留学生や技能実習生はどうなるのでしょうか?
入管法的考えから考察すると
・在留状況が不良
と言うことになります。
在留資格というのは、その在留資格に規定された内容の活動を行うから滞在を許可されています。その該当する活動を行なっていない(留学生のオーバーワークの場合は該当する活動(学業)を目的としているとはいえない)場合は、在留状況が良くないと言うことで
在留資格の更新や変更時には、大幅な減点要因となります。
と言うか通常の(特定技能以外の)在留資格なら普通に更新・変更はできないです。
じゃあ特定技能ならできるのか!?
と言う話になりますが、まあ、結論から言うとケースバイケースになります。
どんなケースなら認められるのか?(弊社の実際の案件ベースの考えであり真実とは限りません)
過去に例として、オーバーワークがかなり多かった留学生が、過去のアルバイトを全て報告し謝罪と今後は法令遵守することを誓い、納税の義務等を履行した場合
や
技能実習生が途中で実習を中断(困難時届提出)した場合でも、本人に帰責性がない場合などは、特定技能への変更が認められました。
在留状況が不良でもいいという勘違いを生んではいけないので
あまり具体的には書かないことにします。。。。。
まあ、そんなこんなで、
現場から特定技能についてでした。
特定技能についても、多分全国でもかなり実績高いと思います(自己調べ)
お問い合わせはお気軽に。
外国人雇用会社必見!必ず行政書士との関係は「点」ではなく「線」で
2020年10月27日(火)
名古屋、行政書士、外国人、顧問、ビザ、在留資格、雇用
A.外国人雇用会社と行政書士と入管行政
1.行政書士とどんなお付き合いをしていますか?
外国人を雇用する会社さんは年々増加していますね!アルバイトを含め外国人と関わりがないという会社さんの方が少なくなってきたかもしれません。
そんな中、以前「外国人採用コンサル」の記事には、外国人採用時の行政書士との関わりについて書きました。
今度は、外国人採用・ビザ(在留資格)手続きが終わり、就労開始した後のお話です。
さまざまな会社さんや同業の入管を専門とされる先生方のお話を聞いていると、行政書士は、基本的に「スポット」で関わっていることが多いようです。
在留資格の申請日が迫ってきたら、行政書士に連絡し(探し)、必要書類を整えて、申請が終わり許可が出たら料金を支払ってまた次回の申請までは特にお互いに連絡はなし。というイメージですね。
はっきり言います!行政書士と会社は「スポット」での付き合い、つまり「点」での関わりをすべきではありません!!特に入管(外国人雇用)関係においては!!
定期的に接触し、情報交換、指導助言を受け入れられる体制を整えるべきです! (税、人事関係においては税理士・社労士さんと顧問契約を結んでいる方は多いのではないでしょうか?!)
つまり、行政書士とも「線」での関わりをするべきなのです。その理由は、入国管理局が出入国在留管理庁へと名称変更(格上げ)されたことにも関係します。
2.入管行政〜「点」の管理から「線」の管理へ〜
ここ数年で在留資格制度は大きく変化しています。
2017年には、技能実習制度が技能実習法の施行とともに、間接規制から直接規制へと変わり(詳細は「技能実習新制度について」)ました。
これにより、外国人技能実習機構という認可法人が設立され、実地検査が定期的に行われるようになりました。
個人的には、立証が不十分な外国人には在留資格を与えない水際対策(言葉不適切?)の入管行政から、受入れを促進し当初の申請内容と食い違っていたら、どんどん指導・行政処分・在留資格取り消ししていきますよーという税務署的行政(言葉不適切?)になったように感じています。
これは、2019年に創設された特定技能も似たような運用をしているなと感じます。登録支援機関や特定技能所属機関(特定技能外国人雇用会社)には、四半期ごとの届出を提出させ、登録支援機関に定期的に指導させるというスタンス。
監理団体も関係性は全然違えど動きは似ていますね。
つまり、何が言いたいかというと、今までは、ビザ(在留資格)更新の申請時点という「点」でのみ入管は外国人の動向を把握していましたが(もちろんそれだけではありませんが、主に、という意味で)、定期報告や実地検査により継続的に「線」で動向を把握するようになりました。
登録支援機関や監理団体などに指導助言させるというところから、もはや「面」での管理といってもいいかもしれませんね。
3.つまるところ、申請の時に急いでつじつまを合わせるようなことは、無意味
↑ということになり、定期的に、専門家である行政書士の指導助言を受け、しっかりとコンプライアンス意識をもって外国人雇用をする必要があるのです。
というか、コンプライアンス遵守しないなら人雇うな。(心の声です)
B.行政書士と「線」で関わる方法
だいたい以下の3つのパターンかなあ。
①教育型
②コンサル型
③請負型
1.教育型:内製化支援
一定期間の契約を定めて、担当者と2人3脚で実務を行っていき、基本的なことはすべて担当者が一人でできるようにしていく、教育型。入管法?ビザ?全然わからんです!って企業さんにお勧め。
ある程度内製化できた後は、②のコンサル型に移ることが多いかな。
2.コンサル型:法的判断委任
基本的なことは一人ででき、基本的な法の仕組みはわかっている。でも、微妙な判断、は心配というときの(別にもなんでも相談でもいいけど、あえて1、と区別するために)もの。
たとえば、エンジニア系・通訳系などの技人国なら、在留資格該当性の判断とか、専攻分野との関連性の判断とか。特定技能なら分野該当性の判断とか。留学生の資格外活動のこととか。いろいろありますよね。
また、現時点で具体的なトラブルがあるわけではなく(もしくは今まで入管に「見逃されてきた」だけの場合等)、現在の申請担当者さんから見ればたいしたものでないと思っていても、まだ表面化していないだけで実は大きな法的リスクを負っているという場合は少なくありません。その潜在的トラブルの洗い出し等。
この点については「専門家に相談するハードルが低くなる」ことも大きなメリットだと思います。早い段階で相談することで事態の深刻化を防ぎやすくなり、現在の担当者さんが対処の難しい案件を抱え込んでしまうリスクを防止することができます。
3.請負型:全部やってよー っていうやつです。(笑)
手続きから、方向性の提案などすべてを一括請負することで、負担を軽減する方法。
従来の行政書士って感じの仕事の仕方ですが、企業にはノウハウはたまらないので、コンプライアンス意識は芽生えにくいかも。というデメリットも。
労働集約業務になるので工数もかかり料金も高くなりがち。
C.上の1.2.のような動きをしている行政書士は少ない
やっぱり行政書士って「代書屋さん」ってイメージが強くて、行政書士自身もそういう風に活動しているセンセーは多い気がしています。
ただのアウトソーシングであれば、ただの暇なヒトみたいな・・・・・(内緒)
専門性があり、ノウハウと経験が豊富だからこそ、線での付き合いを自信もって提案できるわけですよね。
つまりそういう先生がまだまだ少ないということかな。 入管改革というか行政書士改革では。
新たな特定活動始まる!?
2020年8月29日(土)
技能実習/2号修了/特定活動/1年/特定技能/転職/職種/14分野/コロナ/ウイルス|名古屋行政書士
技能実習2号修了+帰国困難=特定活動1年!?
2020年9月より新しい運用が始まるという情報をキャッチしました!
現時点!入管でもまだ公表していない!(多分。ちゃんと見てないだけかも。)
現段階では、コロナウイルスの影響により
「解雇」となった技能実習生が、職種(技能実習時の)を変えての転職が認められています。
技能実習を修了、満了して帰国できない方たちには、帰国困難のための特定活動6月(就労可能)を認めています。
この帰国困難特定活動は、できた当初は従前の会社(技能実習していた会社)で同じ職種をする場合のみでしたが、関連する職種も認めたりと、柔軟性が増した背景があります。(期間も3か月だったんだけど6か月になった!)
そして、9月からは、帰国できない技能実習2号修了者は、特定活動1年を与えて特定技能の移行のための準備(就労)ができるようになるようです!しかも、職種は、特定技能の14分野のどの領域にチェンジしてもOK!!
(追記)
2020/09.04. 製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)はダメっぽいです!
受け付けは9月7日からですよー!とのこと。
この特定技能移行のための特定活動1年の間に新たにチャレンジした職種の業務区分の特定技能試験に合格+N4に合格すれば、特定技能へと切り替えることができるようになります。
N4は技能実習2号を良好に終了している場合は違う職種だから技能試験は受けないといけないけど、日本語試験(N4)のほうは免除できます!
良好に修了とは例えば、随時3級・専門級合格ですね!
よっぽど特定技能外国人を増やすという使命が政府にはあるんでしょうね・・・・・・・・・・・
さてこの在留資格を紹介した理由はここから|紹介業者さん必見!
監理団体でなくても職業紹介(あっせん)が可能!
技能実習生は、派遣業者さん、職業紹介業者さん、参入できません!技能実習生をあっせんできるのは監理団体のみで、監理団体になるためには事業協同組合である必要があるからです。(商工会とか公益社団とかも可能だけどあえて誤解のある感じで書きました)
【あ、組合設立すりゃ―いいんですけどね。当社でも承れますよ!はい!(余談余談。。。)】
しかし、「元」技能実習生である彼ら・彼女らは、特定活動で在留しているため技能実習生ではありません!
つまり!?
職業紹介許可を得てればあっせんが可能なのです。
ビジネスチャンス。
同様の理由から
監理費の徴収も不可能と思われます!(技能実習法の枠組みから出てるので)
そのかわり、支援報酬的な形での請求はできるのではないでしょうか。
組合だって法人なんだから。
現実的に試験合格できんの・・・?
解雇になった技能実習生もほぼ同じようなスキームがあるのですが、
解雇になった実習生(特に日本に来て間もない)は、よっぽど努力のある本人や環境(日本語学習に積極的な会社さん・監理団体さん)のもとで受入れられてない限りN4は難しいかもしれません。
技能試験は業者が結構対策講座とかもできてきてるんでまあそういうのをうまく利用すれば。
しかし、2号を修了した技能実習生は少なくとも丸3年日本で働いているわけですので、努力すればそんなにN4は難しくないと思います。体系的でちゃんとした教育機関なら、N4に1年もかかる人はほぼいないみたいですし。
隠れメリットも実はある|試用期間
表現の語弊を承知で言うと、お互いのお試し期間に使える!
特定技能や技能実習生など(外国人)を受け入れるのに二の足を踏んでいる企業さんでよく聞くのが
「実際うまくいくかどうかわからない」
言葉の都合、文化の都合、社員との関係、お客さんとの関係、ちゃんと仕事ができるのか、高いハードル(ビザの手続きや労務関係の整備)・・・・・
いきなり受け入れるには確かにかなりのハードルがあると思います!
でも、このビザなら1年の間に
本人は会社を、会社は本人を、評価して選ぶことができますよね!
お見合いですね。
(言葉を選べよって感じですよね・・・汗)
まあ、そういうことで、ハードルも少し下がるのではないかと考えています!
この先さらなる緩和も!?
おそらく、試験のこととか特定技能を増やしたい政府としては緩和があるかもしれませんね・・・
新しい職種で1年間ちゃんと働いて、企業さんから一定以上の人事評価をもらった場合は、試験合格免除!とかね!
あ、テキトーに言ってますよ。
まあそんなこんなでこんな案件はプロにお任せよー!
ってだんだん雑になって最後にとても雑!以上!